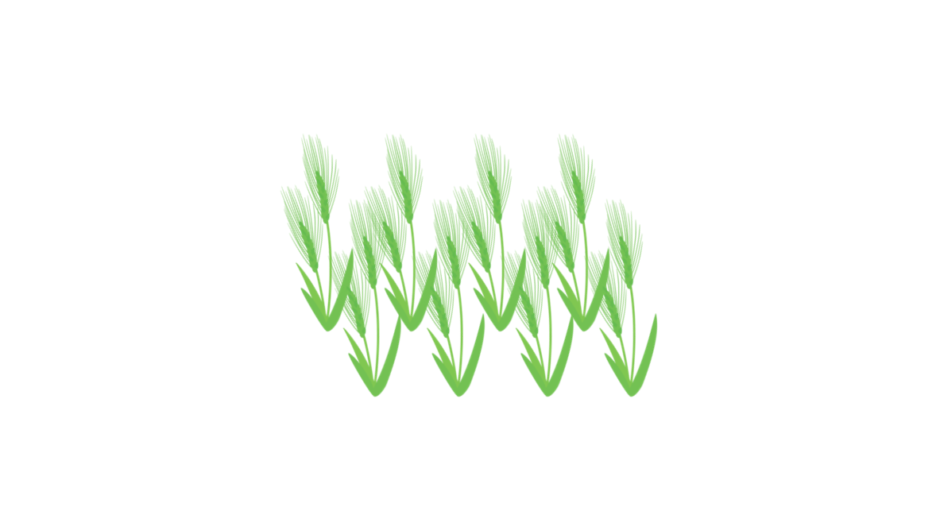土壌改良や強風よけ、害虫対策のために畑を囲む「オオムギ」。道行く人達から「あれなに?」と聞かれる。家庭菜園にオオムギはかなり珍しいようだ

緑肥として種まきをしたオオムギが芽を出し、3週間経って20cmほどの高さに育った。
畳1畳より一回り大きいサイズの小さな畑の周りを取り囲むようにして伸びていくオオムギについて、私はかわいらしいと満足しているのだが、畑の前を通りかかる人には「?」に感じるらしい。
毎朝ゴミ収集場に行くために通る男性、夕方ウォーキングをする3人のおばあ様方等々、芽が出始めた頃から必ず立ち止まってじーっと見つめたり、指を挿してあれこれ言っているのが部屋の中から見える。
外にいれば「あれなに?」と聞かれる。
「オオムギです」と言うと、「ふ~ん・・・」というリアクションだ。
緑肥とは、栽培した植物を土壌にすき込み、肥料として活用する方法で、普段は大きな畑で休耕期間に植えてあるのが良く見る姿だ。
母に写真を送ったら「まあ、ふつう(家庭菜園で)そんなことする人いないものねぇ」と言う。
私が頼りにしている本「NHK趣味の園芸 やさいの時間 自然のチカラで育つ野菜づくり! 有機の菜園12か月」の中で、緑肥は土壌改良や強風よけ、害虫対策というように利用でき、土を育てるために育てよう。とある。
この本の畑はもっと広い面積の家庭菜園なのだが、小さい畑には向いていないとは書いてない。ならやってみようと小さな畑の周囲をぐるっと囲むようにオオムギをまいた。
ついご近所や周囲の目を気にしてしまうのはやめて、やりたかったらやってみる。
もしかしたらこれがこれからの家庭菜園のカタチになっていくかもしれないよ。
(出典:佐倉朗夫.NHK趣味の園芸 やさいの時間 自然のチカラで育つ野菜づくり! 有機の菜園12か月.NHK出版,2025,112p.)
 私が有機栽培で野菜をつくったら~緑肥のタネ(オオムギ)をまく~
私が有機栽培で野菜をつくったら~緑肥のタネ(オオムギ)をまく~
 私が有機栽培で野菜をつくったら~オオムギ発芽~
私が有機栽培で野菜をつくったら~オオムギ発芽~